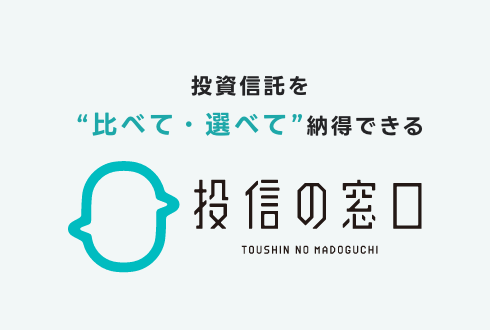新しいNISA制度は非課税期間が無期限に!新旧制度の比較ポイントや注意点を解説
- #新NISA
- #非課税期間
- #制度

2024年1月から新しいNISA制度がスタートしました。
テレビやニュースでよく目にするけれど、「従来の制度と何が違うの?」「そもそもNISAについてあまり知らない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
NISA制度の特徴として、少額で投資ができる、投資の利益が非課税になるなど資産運用を始めやすく、続けやすいといった魅力がありますが、自分にあった資産運用を行うには新旧制度の理解が大切です。
本記事では新NISAについて、旧NISAとの違いや重要ポイントを解説していきます。
新NISAを活用して、将来のための資産運用を始めてみましょう。
いまさら聞けない!そもそもNISA制度とは
NISAとは「少額投資非課税制度」のことで、個人の資産形成を応援する税制優遇制度です。
通常、投資によって得られる利益には約20%の税金がかかります。
しかし、NISA口座を通じて上場株式や投資信託に投資をすると、税金はかかりません。
NISA制度自体は2014年から始まり、2023年までは一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAと3つのNISAがありました。
2024年1月からは従来の制度から大幅な改正が行われ、年間投資枠の拡大や非課税保有期間の無期限化などにより、柔軟な資産形成が可能となりました。
ここからは旧NISAと新NISAの制度の違いをまとめていますので、比較の参考にしてみてください。
旧NISAと新NISAの違いを徹底解説
ここでは、旧NISAと新NISAの違いを表にまとめました。
| 項目 | 旧NISA | 新NISA | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 制度の併用 | 不可 | 可能 | ||
| 年間投資枠 | 120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 800万円 |
1,800万円 ※売却すると投資枠は翌年以降に再利用可能 (1,800万円のうち 成長投資枠は1,200万円まで) |
|
| 非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 | 無期限 | |
| 制度実施期間 | ~2023年末 | 2024年1月~(恒久化) | ||
| 対象年齢 | 18歳以上の成人 | 18歳以上の成人 | ||
| 購入方法 | 一括・積立 | 積立 | 一括・積立 | 積立 |
| 対象商品 | 上場株式・投資信託等 | 金融庁の基準を満たした投資信託に限定 | 上場株式・投資信託等 | 金融庁の基準を満たした投資信託に限定 |
新制度への移行による主な変更点は、以下のとおりです。
●年間投資枠、非課税保有限度額の拡大 ●非課税保有期間の無期限化、制度の恒久化 ●「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能 ●投資枠の再利用が可能
大きな違いとして挙げられるのは、年間投資枠と非課税保有限度額が大幅に拡大した点です。
例えば、旧NISAの一般NISAを選んだ場合は、年間120万円が年間投資枠であった一方で、新NISAの成長投資枠では年間240万円まで投資枠が設けられています。
年間投資枠が旧NISAの2倍となったことで、多くの資金で資産運用ができるようになりました。さらに、つみたて投資枠も併用すれば、新NISAでは年間最大360万円の投資枠を活用することができます。
資産運用の資金を蓄えている方で、旧NISAの年間投資枠では少ないと思っていた方にとっては、制度改正により投資の選択肢が広がったと言えるでしょう。
残り3つの変更点については次で解説します。
新NISAによって改善された3つのポイント
年間投資枠、非課税保有限度額が大幅に拡大した点については既に解説しました。
その他、新制度によって改善された3つのポイントについて解説します。
●非課税保有期間の無期限化、制度の恒久化 ●「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能 ●投資枠の再利用が可能
それぞれ詳しく見ていきましょう。
非課税保有期間の無期限化、制度の恒久化
非課税保有期間の無期限化・制度の恒久化により、投資を始めやすく、売却タイミングも自分で選びやすくなりました。
なぜなら、旧NISAでは一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間の非課税保有期間が設定されていたため、保有期間の終了を意識した運用が必要でした。
特に旧NISAの一般NISAは非課税期間が5年と短く、5年後に投資商品を売却するか、保有する投資商品を翌年の枠に移す(ロールオーバーする)か、課税口座に移すかという選択を迫られていました。
しかし、新NISAでは非課税保有期間が無期限となったため、売却タイミングだけを意識するだけでよく、時間を掛けた資産形成が可能になりました。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能
旧NISAでは、一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選ばなければいけませんでした。
さらに、旧NISAでは、一般NISAとつみたてNISAの変更は年に1回のみ対応できましたが、手続きが煩雑などの理由でNISAの利用に制約を感じる方もいたようです。
新NISAでは、一般NISAとつみたてNISAという名称が以下のように変更され、併用が可能となりました。
【NISA制度の名称】
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 一般NISA | 成長投資枠 |
| つみたてNISA | つみたて投資枠 |
投資枠の再利用が可能
年間投資枠とは、1年間で投資できる枠のことで、使用した額に関係なく毎年更新されます。
旧NISAと新NISAでの年間投資枠の違いは以下のとおりです。
| 一般NISA(旧NISA) | 成長投資枠(新NISA) | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 年間120万円 | 年間240万円 |
| つみたてNISA(旧NISA) | つみたて投資枠(新NISA) | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 年間40万円 | 年間120万円 |
年間投資枠が増えたことで、選択できる商品や月々の積立金額の設定に選択肢が生まれ、より効率的な資産運用が可能になりました。
新NISAのはじめ方
ここでは新NISAの開始手順を3つに分けて説明します。
1.金融機関を選ぶ 2.NISA口座開設を行う 3.投資商品を決める
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.金融機関を選ぶ
最初のステップは適切な金融機関の選択です。
NISA口座を開設するには、NISAを提供している金融機関(銀行や証券会社など)で口座を作る必要があります。
普通の預金口座や証券口座とは異なり、NISA口座は1人につき1口座しか開設できない点に注意してください。
また、口座を別の金融機関に移すには手続きが必要になります。
口座を開設する際は、各金融機関の情報を比較しながら慎重に選びましょう。
新NISAを始めたい方に向けて、証券会社の選び方を記事にまとめておりますのでこちらの記事を参考にしてみてください。
2.NISA口座開設を行う
NISA口座を開設する金融機関を決めたあとは、手続きを行いましょう。
現在は、多くの金融機関でオンラインでの申し込みが可能です。
口座開設に必要な書類の一例は、以下のとおりです。
●非課税口座開設届出書(NISA申請書) ●本人確認書類 ●マイナンバーカード
例として、東海東京証券でNISA口座を開設する際の5つのステップを紹介します。

①NISA口座開設の申し込み
②税務署による申し込み内容の審査
③東海東京証券へ審査結果の通知
④審査結果に問題がなければ口座開設
⑤NISA口座開設完了をお客さまへ通知
オンラインでの口座開設であれば、時間と場所の制約なしに、自分のタイミングでいつでも申し込みが可能です。
3.投資商品を決める
NISA口座開設の完了通知が届いたら、開設した金融機関で取り扱っている投資商品の中から銘柄を選び運用を開始しましょう。
例えば、つみたて投資枠で運用できる投資商品は、2024年4月9日現在で262銘柄となります。年間投資枠の範囲内であれば複数銘柄に投資をすることも可能です。
また、成長投資枠では、投資信託だけでなく国内株式や海外株式など投資対象商品が豊富な点が特徴です。ただし、投資商品は金融機関によっては取り扱いがない商品もありますので、金融機関ごとの投資商品を比較することが大切です。
新NISAに関するよくある質問
ここでは新NISAに関するよくある質問に回答します。
●新NISAでは金融機関を変更できる? ●NISAを始めるのはどのタイミングがベストなの?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
新NISAでは金融機関を変更できる?
NISA制度の内容は変わりましたが、NISA口座は1人1口座しか開設できないという原則は変わりません。
つまり、NISA口座の金融機関変更を行うには、今利用している金融機関にて手続きが必要です。
ここで留意したいのが、金融機関変更を行う年に少しでもNISA口座を利用していた場合、その年に金融機関の変更を行うことはできません。
また、NISA口座の金融機関変更手続きで必要になる書類は、金融機関によって異なります。
ご自身の利用している金融機関に確認するとよいでしょう。
また、新NISAと旧NISAは別の制度ですので、新NISA口座を旧NISA口座とは別の金融機関で開設することも可能です。
旧NISA口座を開設していた方は、同じ金融機関で新NISA口座を開設されている場合がほとんどかと思いますが、金融機関を変更する場合は新NISA口座のみ可能という点に注意してください。
NISAを始めるのはどのタイミングがベストなの?
NISAを始めるタイミングは、早ければ早いほど運用できる期間が長くなります。
運用期間が長いほど複利効果の増加が期待できる点も、早く始めるべき理由の1つといえるでしょう。
複利効果とは、運用で得た利益などを再投資することにより、得られる利益が増えていくことを言います。
金融機関にもよりますが、NISAは少額からでも資産運用を始められる制度です。
生活に必要な最低限の資金と余剰資金を分けて、今からでも始めてみてください。
まとめ
本記事では新しいNISA制度について非課税期間や年間投資枠の違いや具体的なNISA口座の開設方法まで詳しく解説しました。
新しいNISA制度で覚えておきたいポイントは以下の3つです。
●非課税保有期間が無期限 ●つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能 ●年間投資枠の拡大
新しいNISA制度が始まったことで、保有期間の制限なく非課税のメリットを受けながら資産運用ができるようになりました。
ただ、制度が変わったからといって何も調べずに始めるのは避けましょう。
新NISAのメリットとデメリットの両方を理解した上で、将来に向けた資産形成でどのように活用するかが大切です。
今回紹介した内容を踏まえて、新NISAを始めてみてはいかがでしょうか?
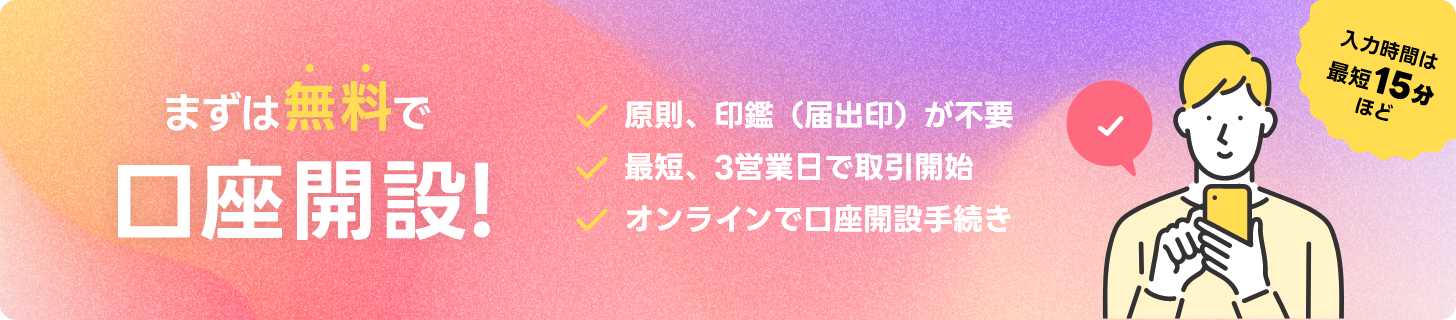

※クリックすると東海東京証券のWEBサイトに移動します。
はじめてNISAをご利用されるお客様は、証券総合取引口座とNISA口座をまとめて開設できます。