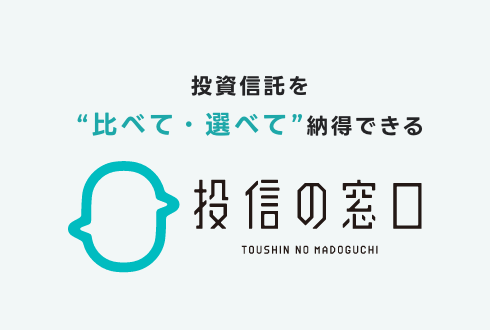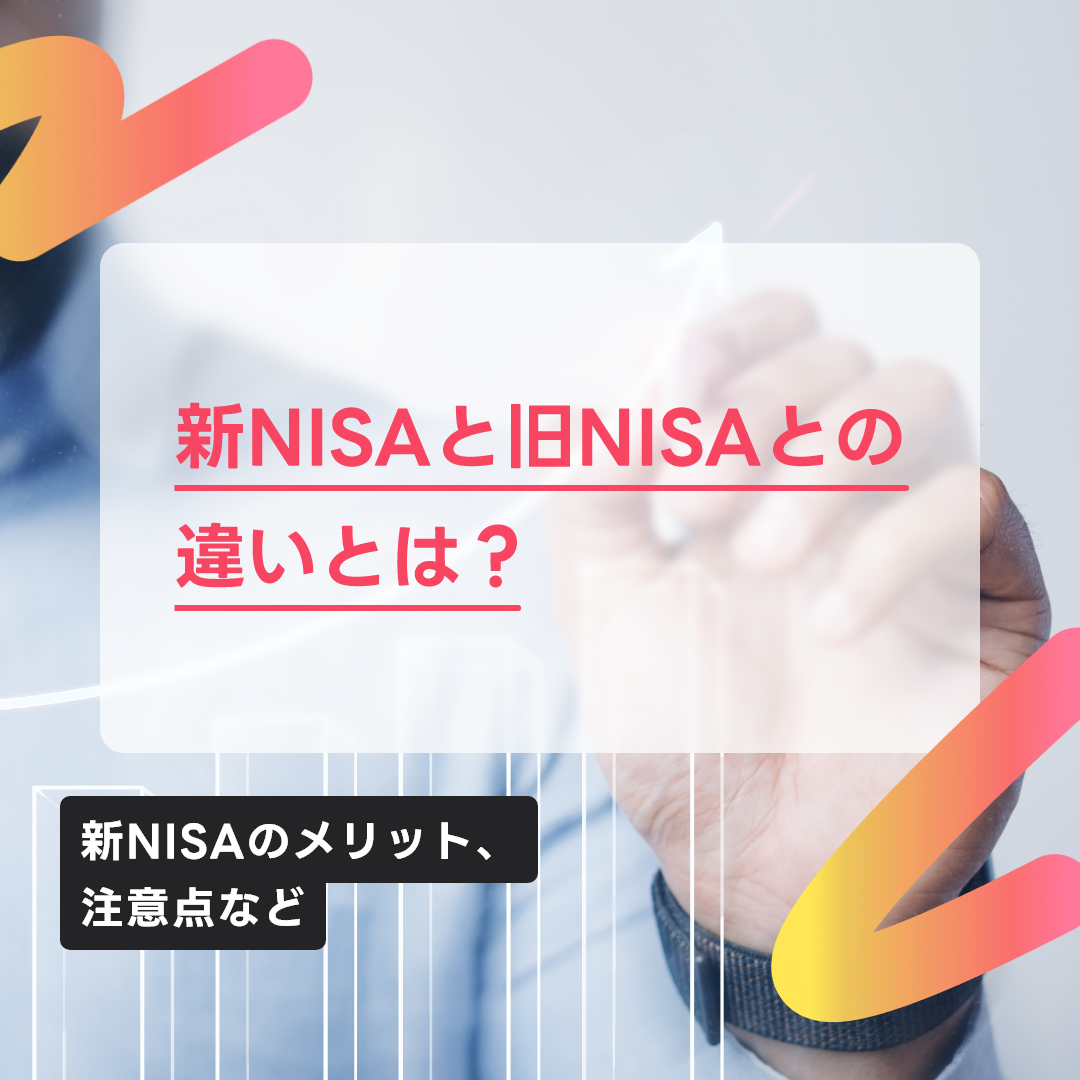
新NISAと旧NISAとの違いとは?新NISAのメリット、注意点など
- #新NISA
- #制度
- #旧NISAとの違い

2024年1月から新NISA制度が始まりました。
つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、非課税保有限度額の上限が拡大されるなど、2023年までの旧NISAと比較すると、大幅に利用しやすい制度になったと言えます。
そこで本記事では、すでに新NISAを始めている方や、これから始めようと検討している方に向けて、新NISAと旧NISAの違いについて解説します。
そもそもNISAとは
NISAとは「ニーサ」と読み、少額からでも投資を始めやすいように設計された「少額投資非課税制度」です。
イギリスのISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)をモデルにし、日本版として制度が整えられていることから、日本版ISAとしてNISA(Nippon Individual Savings Account)と名付けられました。
新NISAと旧NISAの違い
続いて、新NISAと旧NISAの違いについて解説します。ポイントを表にまとめてみました。
| 旧NISA | 新NISA | |||
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 制度の併用 | 不可 | 可能 | ||
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 800万円 | 600万円 |
1,800万円 (うち成長投資枠1,200万円) |
|
| 非課税保有期間 | 20年 | 5年 | 無期限 | |
| 対象商品 | 金融庁の基準を満たした投資信託に限定 | 上場株式・投資信託等 | 金融庁の基準を満たした投資信託に限定 | 上場株式・投資信託等 |
出所:金融庁・投資信託協会をもとに東海東京証券作成
旧NISAでは併用できなかったつみたてNISAと一般NISAが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠という名称に変わり併用できるようになりました。
年間投資枠は、つみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円まで拡大し、非課税保有限度額も最大で1,800万円まで拡大しました。
また、旧NISAでは非課税保有期間がつみたてNISAで20年、一般NISAで5年と制限がありましたが、新NISAでは無期限となりました。
旧NISAと比べて利便性が大きく向上したと言えるでしょう。
新NISAの3つのメリット
続いて、新NISAの3つのメリットについて解説します。ポイントは以下の3つです。
●制度が恒久化されたため、いつでも始められる ●非課税保有期間が無期限になったため、売却タイミングを好きに決められる ●つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができるため、運用方法の自由度が増す
それぞれについて詳しく解説します。
いつでも始められる
新NISAでは、制度が恒久化され、いつでも好きなタイミングで口座開設し、運用を始められるようになりました。
18歳以上であれば新NISAの利用が可能であり、経済状況などに合わせて、より長期的な視点で資産形成に取り組めるようになりました。
売却タイミングを好きに決められる
旧NISAでは、つみたてNISAは最大20年間、一般NISAは最大5年間と、非課税保有期間に制限があったため、決められた期間内で売却や、ロールオーバーを検討する必要がありました。
しかし、新NISAでは、非課税保有期間が無期限になったため、ライフイベントに合わせ必要なタイミングで投資商品を売却することができるようになりました。
つみたて投資枠・成長投資枠の両方で運用できる
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。
例えば、つみたて投資枠で毎月3万円の積立投資を行い、まとまった資金ができたときに成長投資枠で株式に投資するといった方法が可能になりました。
また、つみたて投資枠で対象のほとんどの商品は、成長投資枠でも投資が可能です。
投資資金に余裕がある方は、つみたて投資枠対象商品を毎月、つみたて投資枠で10万円、成長投資枠で20万円積み立てることで、年間投資枠最大の360万円買付することもできます。
ご自身の運用目的に合わせて、柔軟に制度を活用できるようになった点はメリットと言えるでしょう。
新NISAの注意点を解説
ここまで、新NISAのメリットについて解説してきましたが、注意点があることにも留意しておきましょう。
新NISA口座は各金融機関を通じて1つのみ
旧NISAと同様、新NISA口座は1人につき1口座のみ開設可能です。複数の金融機関でNISA口座を開設することはできません。
また、新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となりましたが、それぞれの枠を別々の金融機関で開設することができない点には注意が必要です。
金融機関ごとに取扱商品や各種手数料は異なる
新NISAで投資できる商品は数多くありますが、金融機関によっては取扱商品に違いがあります。
例えば、銀行では株式を取り扱っておらず、また、証券会社によっては外国株式の取り扱いがない場合もあります。取引手数料についても金融機関によっては無料としているところもあります。
長期的に投資を続けていく上で、自分の投資したい商品があるか、手数料やサービスが見合っているかなどをしっかり調べ、口座開設する金融機関を決めましょう。
これまでのNISAはどうなる?知っておきたいポイント4つ
さて、2024年1月よりも前に旧NISAで運用していた方は「投資していた商品はどうなるのか?」と気になるかもしれません。
旧NISAについて覚えておくべきポイントは以下の4つです。
●新規の積立や買付は不可 ●最大2042年(20年間)まで非課税期間が継続 ●非課税期間終了後は課税口座へ移管 ●新NISAへの移管は不可
それぞれについて詳しく解説します。
1.新規の積立や買付は不可
旧NISAは、2023年12月で積立や買付の可能期間が終了していますので、非課税投資枠が残っていたとしても、遡って買付を行うことはできません。
2.最大2042年(20年間)まで非課税期間が継続
つみたてNISAの場合は最大20年間、一般NISAの場合は最大5年間の非課税保有期間が設定されていましたので、2023年につみたてNISAで投資した商品は最大2042年まで、一般NISAで投資した商品は最大2027年まで運用を続けることができます。
なお、新NISAと旧NISAは別の制度であるため、新NISAの非課税投資枠は旧NISAの運用状況によって影響を受けることはありません。
3.非課税期間終了後は課税口座へ移管
旧NISAにおける一般NISAでは、非課税期間終了後に保有商品を翌年の非課税投資枠に移す「ロールオーバー」が可能でしたが、2024年以降は実施できません。
そのため、非課税期間終了後は課税口座に移管または売却のいずれかを選択することになります。
4.新NISAへの移管は不可
旧NISAで投資している商品を、そのまま新NISAへ移管することはできません。
先ほども解説したように、旧NISAと新NISAは別の制度であるため、旧NISAで保有する商品を新NISAに移したい場合は、一度売却し現金化してから新NISAで買付する必要があります。
まとめ
新NISAと旧NISAでは、違う点がさまざまあります。
一例として、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能で、非課税保有限度額が最大1,800万円、年間投資枠が最大360万円に拡大されたことから、より多くのお金を非課税で投資できるようになりました。
しかし、制度の拡充により選択肢が広がったことで、商品や投資枠の使い方に悩んだり、利用手続きについて不安を持たれる方もいるかもしれません。
NISAセンターでは、NISAに関する専用相談窓口を設けており、どなたでもご利用いただくことが可能です。また、「NISAがわかる、NISAを始める、NISAを続けるための拠り所」をコンセプトに、各種SNSでNISAや投資に関するよくある質問にお答えしたコンテンツなどさまざまな情報を配信しています。
ぜひフォローしていただき、お気軽にお問い合わせください。
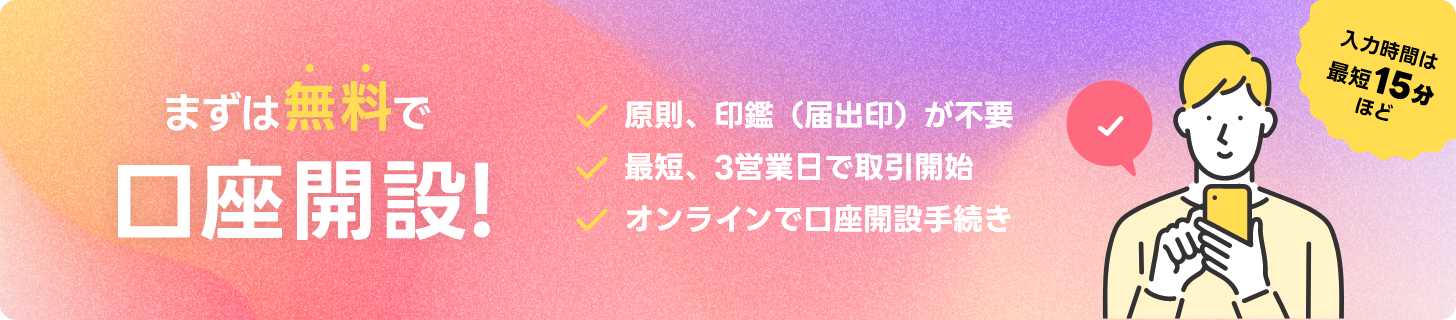

※クリックすると東海東京証券のWEBサイトに移動します。
はじめてNISAをご利用されるお客様は、証券総合取引口座とNISA口座をまとめて開設できます。