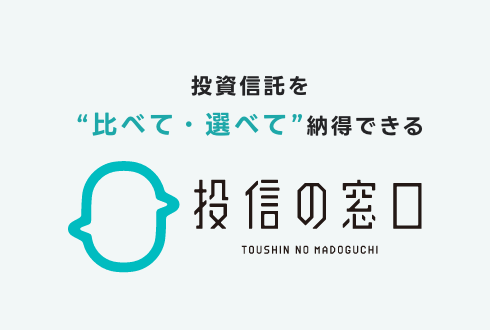新NISAの始め方とは?口座開設の仕方や注意点、金融機関の選び方など
- #新NISA
- #NISAの始め方
- #証券会社

新NISAについて調べていて、少しずつ制度の内容などが理解できてきたら、実際に新NISAはどのように始めるのか気になる方もいるでしょう。
そこで本記事では、新NISAの始め方について解説します。実際に新NISAを始めるイメージを具体的に描きたい方にとって参考になる情報をまとめているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
※以下、特に断りがない場合、NISAとは2024年からスタートした新NISAのことを指します
NISAの始め方
まず、NISAの始め方を大まかに説明します。全体的な流れは以下の通りです。
①金融機関を選んでNISA口座開設を申し込む
②NISA口座開設の完了を確認する
③投資する商品を選ぶ
④NISA口座で商品を購入する
NISAを始めるためには、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座を開設する必要があります。ただし、NISA口座のみを開設することはできず、例えば証券会社では証券口座も開設する必要があります。
また、NISA口座は1人につき1口座という制限があります。税務署がきちんと確かめるため、重複してNISA口座を持つことはできません。ただし、1年単位で金融機関を変更することはできます。
中には2023年末までに旧NISA口座を開設していた方もいるかもしれません。そのような方は、手続きをしなくても旧NISA口座を開設している金融機関で、新NISA口座が自動的に開設されているので、金融機関に確認してみるとよいでしょう。
NISA口座開設の流れ
さて、NISA口座開設について、さらに詳しく説明します。すでに証券口座などをお持ちで、ネットでNISA口座開設を行う方の流れは以下の通りです。
①必要書類を用意する
②金融機関の公式サイトで必要情報を入力する
③必要書類をアップロードしてNISA口座開設を申し込む
④金融機関に税務署の審査結果が届く
⑤NISA口座が開設される
ほとんどの金融機関では、ネットでNISA口座を開設できるようになっています。基本的には、画面上に表示される指示に従って必要な情報を入力していくだけなので、比較的簡単に開設可能です。
必要書類とは
先ほど説明した通り、口座開設は基本的には画面の指示に従って入力していきますが、必要な書類が不足していると口座開設がスムーズに進みません。そこで、必要書類は何を準備すればよいのか 、東海東京証券を例に具体的にお伝えします。
<必要書類>
①マイナンバーを提出している場合
・非課税口座開設届出書
・本人確認書
②マイナンバーを提出していない場合
・非課税口座開設届出書
・個人番号告知書
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類など
本人確認書類は、運転免許証・パスポート・各種健康保険証・介護保険証・印鑑登録証明書などが該当します。
そして、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類としては、以下①~③のいずれかになります。
①個人番号カード(両面)
②通知カード(※)+本人確認書類(顔写真付は1種類、または顔写真のないもの2種類)
③個人番号付きの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」+本人確認書類(顔写真付または顔写真なし1種類)
※「通知カード」は、記載された住所、氏名、個人番号と東海東京証券に届出される住所、氏名、個人番号が同じ場合にのみ利用できます
さらに詳しく東海東京証券でNISA口座を開設する手順を知りたい方は、 こちらを確認してみてください。
NISAを始めるときに注意すること
続いて、NISAを始めるときに注意することを3つ紹介します。
●1人につき1口座のみ開設できる
●申込から口座開設まで時間がかかる
●毎月の積立金額には上限がある
それぞれについて深掘りします。
1人につき1口座のみ開設できる
NISA口座は、1人につき1口座しか開設できません。
金融機関にNISA口座開設の申込を行うと、その金融機関が税務署へ重複申請がないかを確認します。重複申請があった場合(他の金融機関でNISA口座を開設していた場合)には、申込は無効となります。
申込から口座開設まで時間がかかる
NISA口座開設の申込をしてから、口座が開設されるまでには時間がかかります。前述のように税務署への確認もあるため、多くの場合、2~3週間ほどの時間がかかります。
一部の金融機関では、税務署の審査結果がわかる前に、先にNISA口座の仮開設ができるところもあり、最短で申込当日に仮開設が行われ、積立などの取引が可能となります。ただし、他の金融機関との重複が判明した際には、開設された口座が無効となりますので注意が必要です。
非課税で運用できる金額には上限がある
NISAでは、非課税で運用できる金額に上限があります。改めて、NISAの特徴について、表でまとめると、以下のようになります。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 制度の併用 | 可能 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(うち、成長投資枠1,200万円) | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 買付方法 | 積立 | 一括・積立 |
出所:金融庁ホームページをもとに東海東京証券作成
年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。また、非課税保有限度額は1,800万円で、そのうち成長投資枠は1,200万円となっています。
なお、NISAで買付した商品を売却した場合、非課税枠を再利用することができます。注意点としては、売却した商品の取得価額分が新たな投資に利用可能となるのは、翌年以降となります。そして、非課税枠を再利用する場合であっても、年間投資枠上限の360万円(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)を超えることはできません。
NISA口座を開設する金融機関の選び方
ここからは、NISA口座を開設する金融機関の選び方について解説します。主なポイントは、以下の3つです。
●商品ラインアップ
●購入時手数料と提供サービス
●セミナーや投資情報の充実
それぞれについて深掘りします。
商品ラインアップ
投資できる商品のラインアップは、金融機関によって異なります。例えば、銀行では株式を取り扱っていません。また、つみたて投資枠で投資可能な投資信託は、金融庁が定める条件を満たした中から、金融機関がそれぞれの方針に従って決めています。
そのため、投資したいと思っていた商品がないということも考えられます。金融機関を決める際は、投資したい商品を取り扱っているか必ず確認してください。なお、まだ商品を決めていない場合は、取り扱い商品が多いところを選ぶのがおすすめです。
購入時手数料と提供サービス
金融機関によって購入時手数料は異なります。例えば一部の証券会社では、国内株式の購入時手数料を無料としているところもあります。また、金融機関によって提供しているサービスも異なります。クレジットカードでの積立投資やポイントサービス、最低購入金額などいろいろなサービスがあるので、自分に合った金融機関を選ぶとよいでしょう。
セミナーや投資情報の充実
セミナーの開催、投資に関する情報は金融機関によって異なります。また、金融機関によっては、口座を開設している方だけが参加できるセミナー、閲覧・視聴が可能な投資情報などもあります。自分が見やすい、わかりやすい情報を発信している金融機関を選ぶのも大切です。
まとめ
今回は、NISA口座開設の仕方や注意点、金融機関の選び方などについて解説しました。
「少し複雑そうだな」という印象を持たれた方もいるかもしれませんが、大変なのは最初のNISA口座開設くらいです。それも、必要書類を集めたら、問題なく進められるでしょう。
口座開設以降は、商品を選び運用を継続することが重要です。しかし相場の動きをみて、時にはこのまま保有していてもよいのか、他に良い商品があるのではないかと疑問に思うこともあるでしょう。
NISAセンターでは専門スタッフがフラットな立場で相談対応をしています。お気軽にNISAセンター専用ダイヤルまでお問い合わせください。
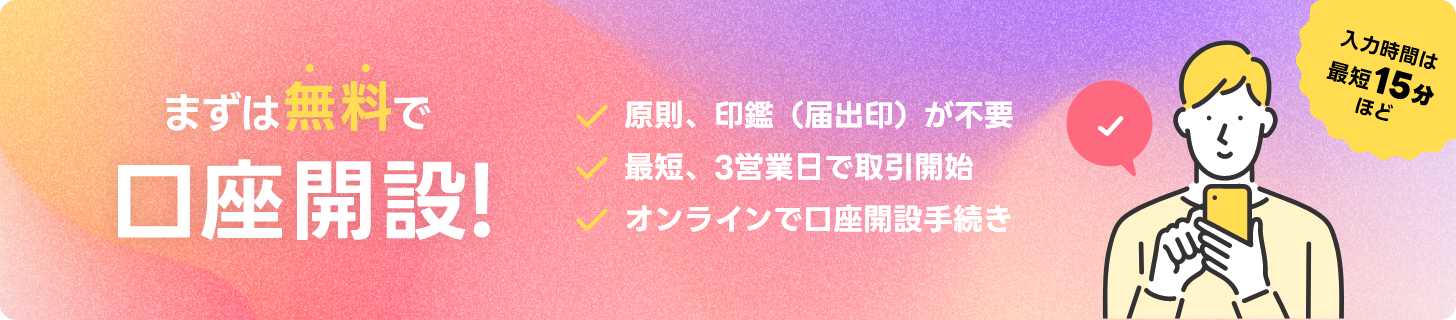

※クリックすると東海東京証券のWEBサイトに移動します。
はじめてNISAをご利用されるお客様は、証券総合取引口座とNISA口座をまとめて開設できます。