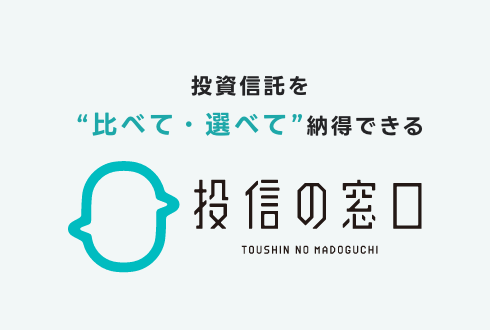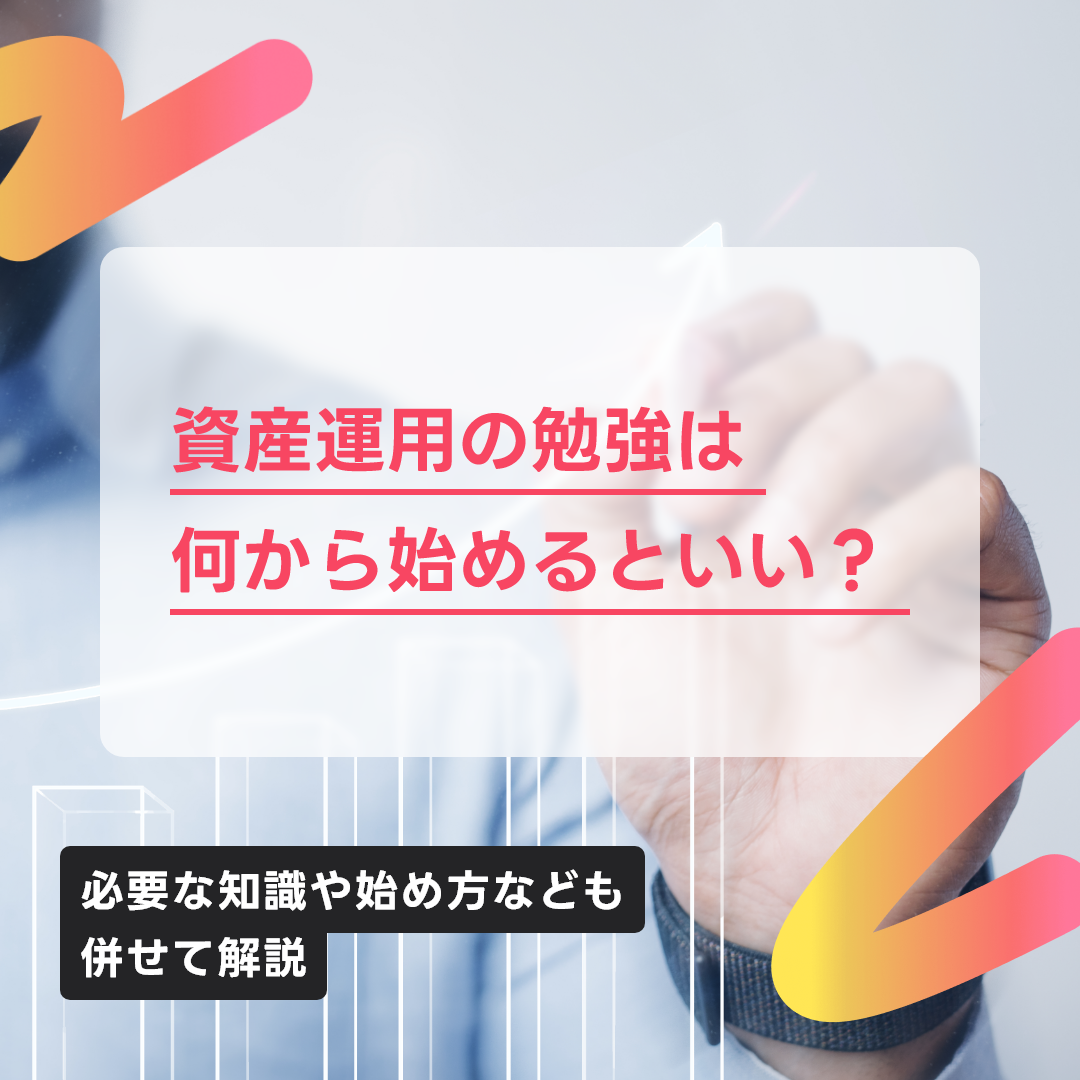
資産運用の勉強は何から始めるといい?必要な知識や始め方なども併せて解説
- #資産運用
- #長期目線
- #分散投資

NISAやiDeCoなど資産運用の話題が多く聞こえるようになってきました。物価上昇への備えや老後の資金準備、FIREを目指したいなど、資産運用を始める理由はさまざまあると思います。
しかし、資産運用にはメリットだけではなくデメリットもあり、資産が減ってしまう可能性がゼロではありません。そこで、必ずやっておきたいのが、資産運用の勉強です。
本記事では、資産運用の勉強方法や勉強を始める前に知っておきたいこと、資産運用を行う上での注意点などについて解説します。
資産運用の勉強を始めたいけれども、どこから手を付けたらよいかわからない方は、ぜひ読んでみてください。
資産運用の勉強を始める前に知っておきたいこと
まず、資産運用の勉強を始める前に知っておきたいことを紹介します。ポイントは以下の3つです。
●そもそも資産運用とは?
●資産運用を行うメリット
●資産運用を行うデメリット
それぞれについて詳しく解説します。
そもそも資産運用とは?
そもそも資産運用とは、自分が持っているお金(資産)を株式や外貨資産などに配分することで効率的にお金を増やしていくことを指します。
資産運用というと、株式などへの投資をイメージする方も多いかと思われますが、預貯金も資産運用のひとつです。お金の増え方は小さいですが、一定金額の元本保証があって、原則いつでも現金化できるという特徴を持っています。
資産運用を行うメリット
資産運用を行う最大のメリットは、資産運用を通して自分が持っているお金が大きく増える可能性があるところです。
資産運用を適切に行うことができれば、自分が働かなくてもお金が手に入る「不労所得」を得ることができるかもしれません。
また、運用する商品によっては複利で運用することができ、投資期間が長くなるほど複利効果で大きな利益を得られる可能性もあります。
資産運用を行うデメリット
対して、資産運用を行う最大のデメリットは、元本割れを起こす可能性があるところです。
元本割れとは、資産の価格変動などが原因となり、当初投資した(預けた)元本よりも少ない金額しか戻らない状況のことを言います。
投資には常にリスクが付きもので、お金を増やすつもりで資産運用を始めたのにもかかわらず、反対にお金が減ってしまった、という状況にもなりかねません。
しかし、そのリスクをなるべく抑える方法として、「長期・積立・分散」を意識した投資を心掛けるとよいと言えます。「長期・積立・分散」投資については、金融庁も資産形成を行う上でのポイントとして推奨しています。
資産運用を始める際は、得られる可能性のある利益だけを見るのではなく、失う可能性についてもきちんと見定めましょう。
資産運用の勉強方法
投資初心者の方が資産運用について勉強するなら、以下3つの方法がおすすめです。
●金融機関が公開している動画の視聴やセミナーを受講する
●有識者の書籍やインターネット記事を読む
●金融に関する資格勉強を通して理解する
それぞれについて解説します。
金融機関が公開している動画の視聴やセミナーを受講する
資産運用は専門用語や経済指標の理解などが必要で、始めるまでの手続きも少し複雑なため、何から手を付けてよいかわからないことが多くあります。そこで、わかりやすくまとめている動画の視聴やセミナーを受講するのがおすすめです。
ここで大切なポイントは「金融機関が公開、運営しているもの」というところです。
現在はSNSが普及し、誰でも気軽に情報発信ができるようになりました。専門的な知識を持っていない方が誤った情報を発信している、また投資詐欺のような情報もあるため、金融機関などの信頼できる情報を得ることが重要です。
例えば、東海東京証券では、無料で動画やセミナーを受講できるようになっています。東海東京TVの動画は投資に関する情報を動画でわかりやすく解説しているので、これから資産運用の勉強をしようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
東海東京TVの動画を視聴する
東海東京証券のセミナー情報はこちら
有識者の書籍やインターネット記事を読む
有識者の方が書かれた書籍やインターネット記事で勉強するのもおすすめです。
書籍やインターネット記事であれば、あとで何度も読み返したり自分の理解度に合わせて読み進めたりしやすいでしょう。
書籍を読んで、不明点があれば、その都度インターネットで検索する方法も有効です。最近では、図やイラストで説明されているわかりやすいものがたくさんあるので、ぜひ書店に足を運んでみてください。
金融に関する資格勉強を通して理解する
資格勉強を通して資産運用の知識を身に付けていく方法もあります。とりわけおすすめなのが、ファイナンシャルプランナーの資格です。
ファイナンシャルプランナーとは、人生の夢や目標を達成するために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く手助けをする人のことです。
日々の家計はもちろんのこと、税制や不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が求められます。そのなかには、資産運用も含まれ、幅広い知識を身に付け、多角的な視点を持つことができるようになるでしょう。
資産運用の始め方
ここからは、資産運用の始め方について解説します。資産運用を始めるには、以下の3ステップで始めるとよいでしょう。
1.目標を設定する
2.資金を準備する+資産運用の勉強をする
3.資産運用を開始する
それぞれ順を追って説明します。
①目標を設定する
まずは、いつまでにいくらの資産を形成するのか、目標を設定しましょう。
例えば、現在40歳で65歳に仕事を退職し、退職後の生活費として3,000万円を現役時代に準備するとしましょう。
現在の資産や今後の収入を想定、逆算した場合に、25年間で2,000万円を貯める必要がありそうだとわかったとします。
単純計算で毎年80万円(毎月約6.7万円)貯めることができれば目標達成できますが、金融庁の「つみたてシミュレーター」で算出すると、毎月3.5万円を25年間積み立て、年利5%で運用できれば2,084万円となり、少ない金額で目標達成することがわかります。
あくまでシミュレーションなので、確実な成果は約束されていませんが、目標達成に向け毎月の積立金額がイメージできるかと思います。
②資金を準備する+資産運用の勉強をする
次に、資金の準備と資産運用の勉強を同時に始めるのがおすすめです。
資金の準備も資産運用の勉強も、長い期間を要するため、じっくり腰を据えて行うようにするのが理想的です。
ここでのポイントは、何かあったときのために備えるお金は、資産運用のお金と別に管理することです。
いまは健康で仕事があるという状況かもしれませんが、突然体調を崩してしまい、収入が不安定になるかもしれません。
一般的には、夫婦共働きの場合は生活費の3か月分、どちらか一方が働いている、もしくは、単身者の場合は生活費の6か月分程度を万が一の事態に備えて用意しておきたいとされています。
また、積立投資など毎月定額投資を行う場合は、生活費に影響を与えない範囲で金額を設定することが重要です。
いずれにしても、余裕資金の範囲で投資を行うことが重要です。
③資産運用を開始する
最後に、実際に資産運用を開始することになります。まずは、少額投資から始めて、「資産運用とはこういったものなのだ」と理解することが大切です。
資産運用するために選んだ金融商品によって、経済動向の影響を受ける度合いが変わることもあるため、経済の動きにもアンテナを張っておくとよいでしょう。
金融商品の例は以下の通りです。
●銀行預金 ●国債 ●社債 ●株式 ●投資信託
このなかで株式や投資信託はNISAで投資することもできます。NISAの始め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事も読んでみてください。
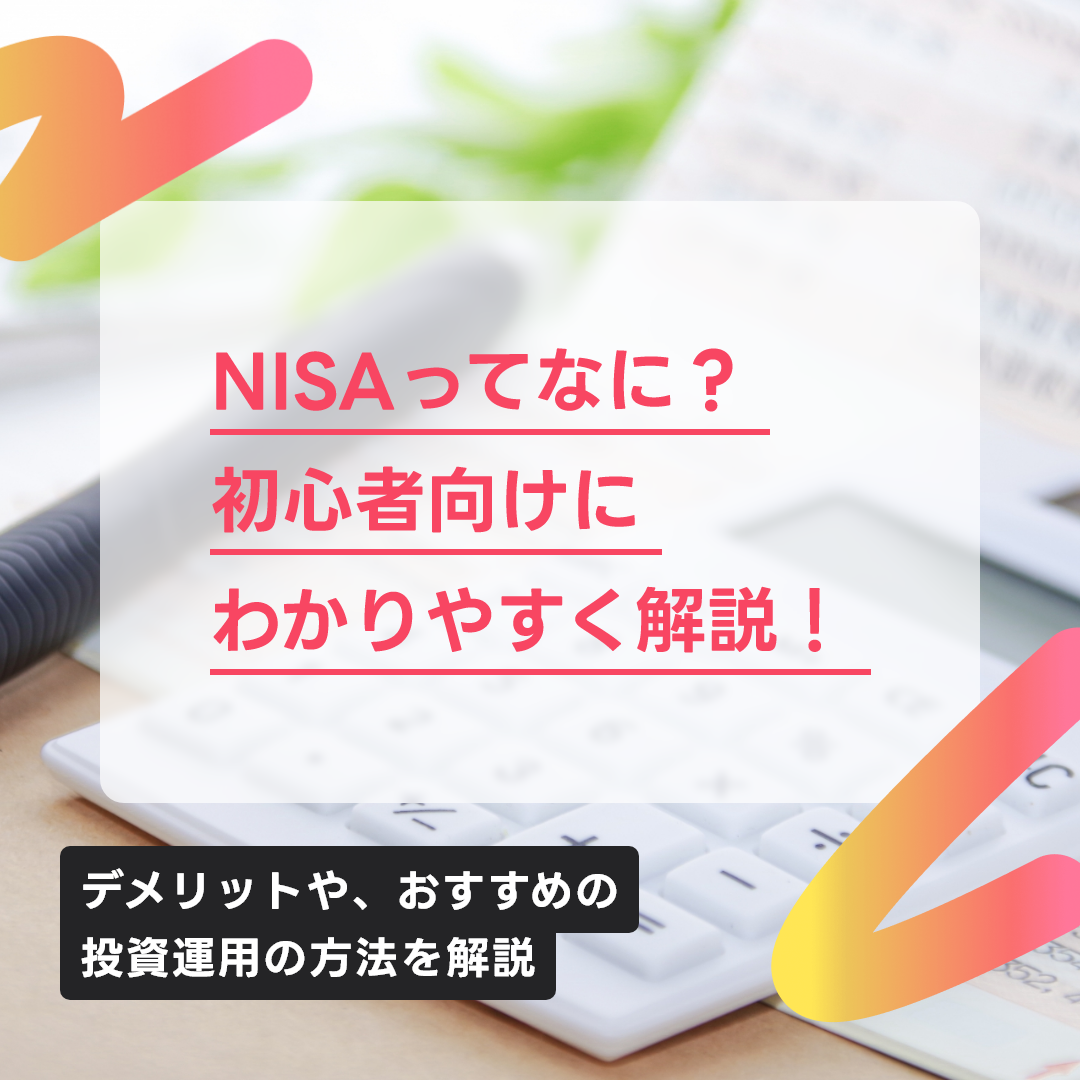
【初心者向け】NISAってなに?メリットやデメリット、始め方などを紹介
2024.07.26
資産運用する上での注意点
資産運用する上での注意点として、2つ挙げられます。
●派手な運用実績に翻弄されない
●長期・積立・分散投資を中心に自分の投資スタイルを崩さない
それぞれについて解説します。
派手な運用実績に翻弄されない
資産運用への注目度が上がるにつれて、多くの投資情報が次から次へと発信されるようになりました。
しかし、そのなかには投資詐欺が含まれていることもあります。
とりわけ「1年で1億円の利益を稼ぐ投資手法」、「億り人(資産運用で億単位の資産を築いた投資家のこと)になるのは簡単」など、派手な運用実績を声高に主張する情報に惑わされたり翻弄されたりしないでください。
一般的には簡単に多くの利益を得ることはできませんし、ハイリターンにはハイリスクが付きものです。
実際に、投資詐欺で何千万円ものお金を失ったとニュースなどで報道されたりもしています。金融庁や金融機関が公式に発表している情報を頼りにして、信憑性のある知識を身に付けてください。
長期・積立・分散投資を中心に自分の投資スタイルを崩さない
資産運用の基本はあくまでも「長期・積立・分散」投資です。
●長期:複利を活用しながら長期的な投資期間で利益を得る ●積立:少額を自動で積み立て続ける ●分散:購入タイミングや投資商品などを分けることでリスクを抑える
この点に優れているのが、NISAのつみたて投資枠です。NISAのつみたて投資枠では、長期・積立・分散に適している投資信託へ積立投資することができます。
NISAのつみたて投資枠に興味がある方は、こちらの記事も読んでみてください。これから資産運用の勉強を始めようとしている方にもおすすめできるわかりやすい内容となっています。
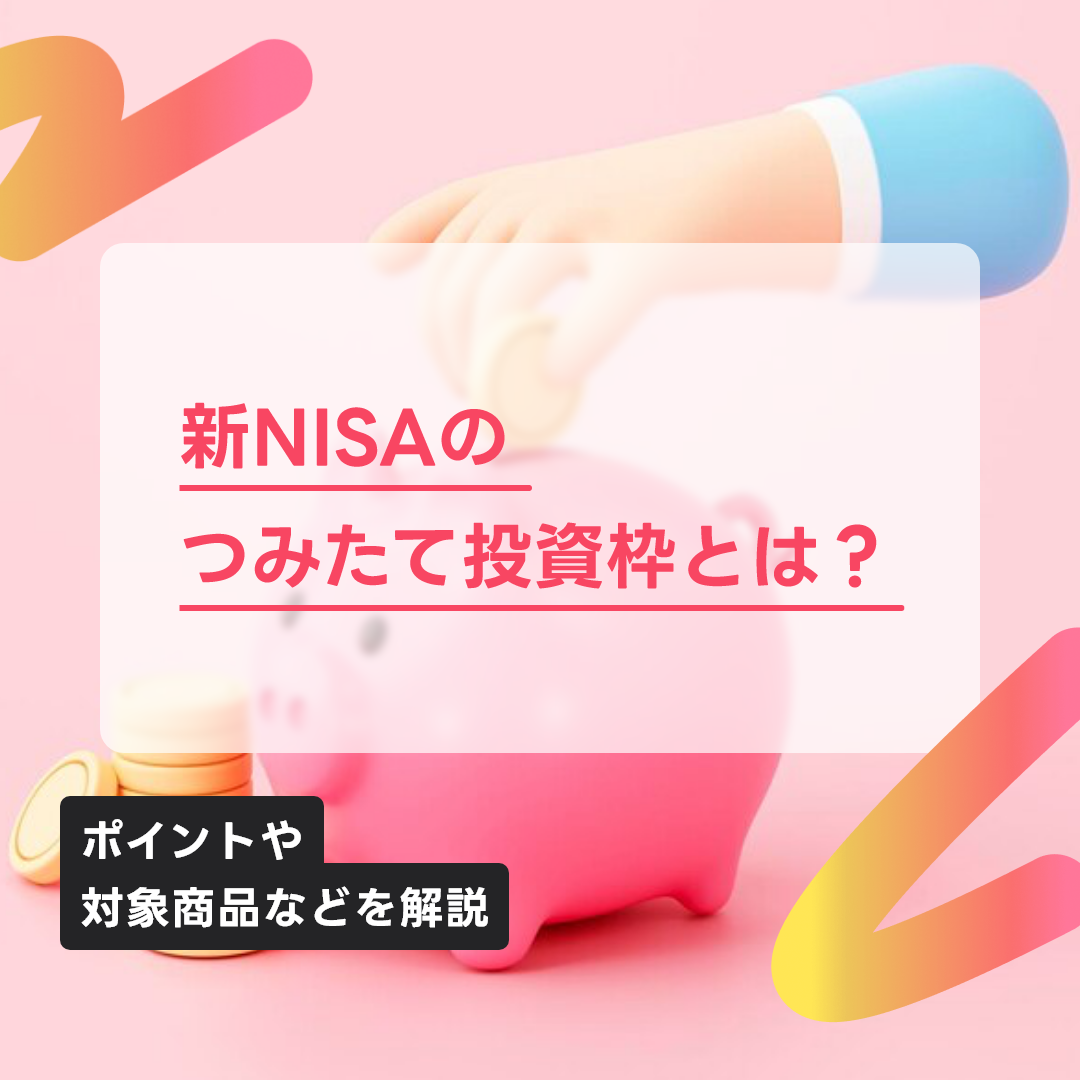
新NISAのつみたて投資枠とは?ポイントや対象商品などを解説
2024.07.05
まとめ
資産運用の勉強を始める際は、根拠が不確かな怪しい情報に惑わされないということが大切です。
ここでポイントになるのが、「どこが発信している情報か」というところで、金融庁や金融機関などの信頼性がある情報を得るようにしましょう。
NISAセンターでは、わかりやすく正確な情報を得ることができるコンテンツを多く掲載しています。資産運用を始めたい方や金融リテラシーを向上させたい方は、ぜひさまざまな記事をご覧ください。
また、YouTubeには、記事にはない内容も取り揃えていますので、ぜひこちらもご覧ください。
NISAセンターYouTubeを見る
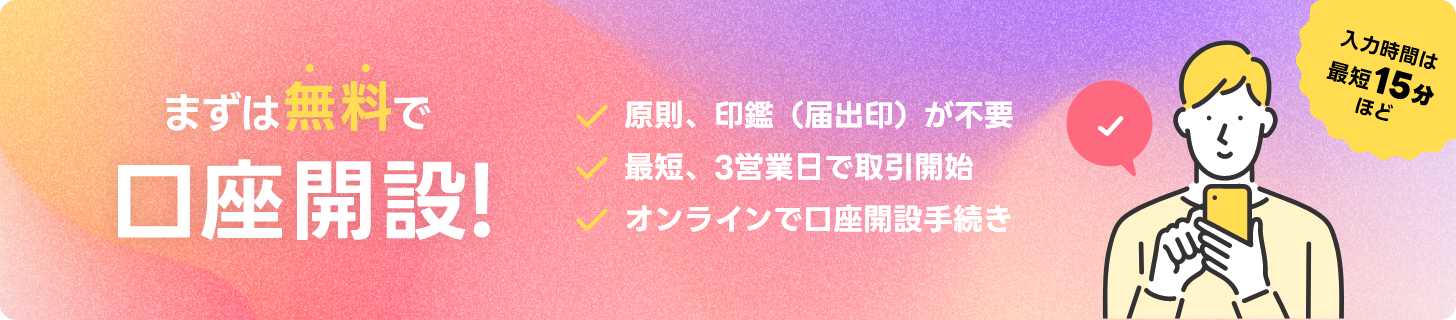

※クリックすると東海東京証券のWEBサイトに移動します。
はじめてNISAをご利用されるお客様は、証券総合取引口座とNISA口座をまとめて開設できます。