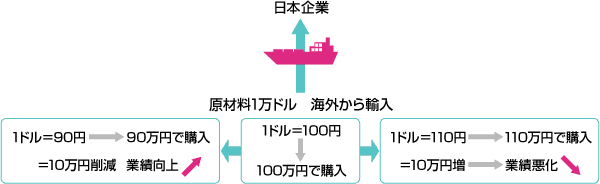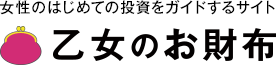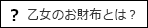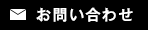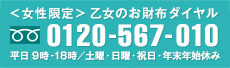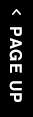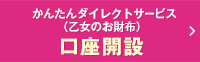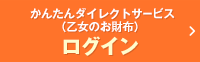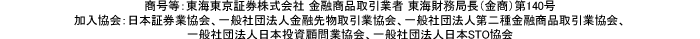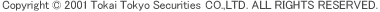株式株価はなぜ動くの?
株価は、買い手(需要)と売り手(供給)の、それぞれの希望する値段と数(株式数)のバランスにより決まります。買いたい人が増えると株価は上がり、売りたい人が増えると下がります。
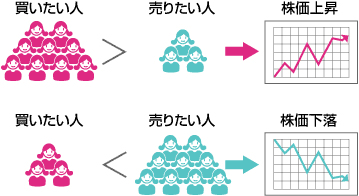
株価の変動要因
株価の動きを予測するためには、いくつかのポイントがあります。
1. 企業業績
株価を決める最大の要因です。特に、今後の業績をみきわめることが重要なポイントになります。企業業績の情報収集には、新聞、会社四季報のほか、テレビ、インターネット、証券会社などによるレポート、雑誌などが参考になります。
2. 世界や日本の政治・経済の動き
国内外の景気、金利、為替の動きなどをウオッチしておくことも大切です。一般的に好景気になれば企業業績が良くなるため株価は上がり、不景気になれば企業業績が悪くなり株価も下がります。また、金利が上がると株価は下がり、反対に金利が下がると株価は上がるといわれています。そのほか、円高になると輸入企業にメリットがあり、円安になると輸出企業にメリットがあります。
3. 市場内部要因
株式市場特有の要因が、株価に影響します。株価は株式の需給関係に左右されます。その他、株価がもつ特異な動きもあります。
4. その他
税制や投資に関するルール(規制)、天候や災害の自然環境、戦争なども株価に影響することがあります。
景気と株価
景気とは、経済動向のこと。経済状態が良いことを「好景気」または「好況」といい、悪いことを「不景気」または「不況」といいます。景気は好不況を繰り返し、循環するといわれています。
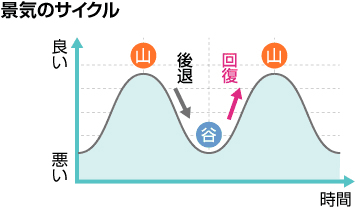
株価を予測するためには、景気を見ることが大事です。なぜならば、株式市場全体が景気と密接に繋がっているからです。一般に好景気になれば企業業績が良くなり株価は上がり、不景気になれば企業業績が悪くなり株価は下がります。
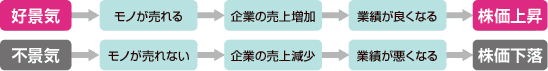
「景気循環について」
- 景気が良いと、売買や取引が活発に行なわれます。人々の購買意欲・購買力が大きくなり、モノがたくさん売れるようになります。モノが売れたら、企業は生産量を増やすため、仕事が増えて、業績もあがります。
- けれども、「作れば売れる」という状況がいつまでも続くわけではありません。大事なのは、需要と供給のバランス。作り過ぎると、モノが余ってしまい、モノの値段(物価)が下がり始めます。
- 値下げをすれば、余ったモノも売れるようになりますが、在庫を減らすには時間がかかってしまいます。在庫がたまると、企業は生産量を減らします。仕事も減り、企業の業績が悪くなってしまいます。
- けれども、必要最低限の消費は保たれるので、物価はある水準で下げ止まります。そこから徐々に消費が増えれば、回復に向かいます。消費が上向けば、企業は再び生産量を増やします。このように景気は循環しています。
- * 景気循環の要因となる一例です。
金利と株価
一般的に、金利が上がると株価は下がるといわれています。反対に、金利が下がると株価は上がるといわれています。
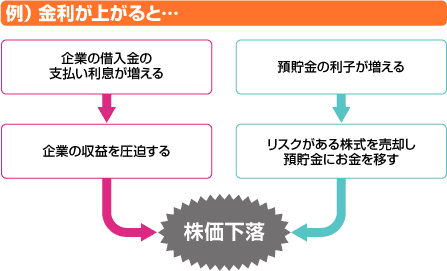
金利が上がると・・・
- 1. 企業経営と金利
- 金利が上がると、企業の借入金の支払い利息が増え、企業の収益が圧迫されます。また、企業は新たな借入れがしにくくなります。資金がなければ事業を縮小します。それにより売上げや利益が減り、株価が下がることになります。
- 2. 投資家と金利
- 金利が上がると、株式より安全性の高い預貯金などへ資金を預けようとする人が増えます。株式に比べリスクが小さく、そこそこの金利が期待できれば、わざわざ株式投資をする人が減るのも当然のことでしょう。そこで、株式を売却して、その資金が預貯金に向かうため、株価は下がることになります。
- * 上記の内容は金利が上がるときの一般的な考え方ですが、株価の変動要因は金利以外にもたくさんあります。
為替と株価
円高・円安の動きは、輸出入を行なっている企業に影響を与えます。一般的に、円高になると輸入企業にメリットがあり、円安になると輸出企業にメリットがあります。ただし、急激な為替の変動は、株式市場だけでなく経済全体に影響を与えますので、政府が介入して急激な変動を抑えようとすることもあります。
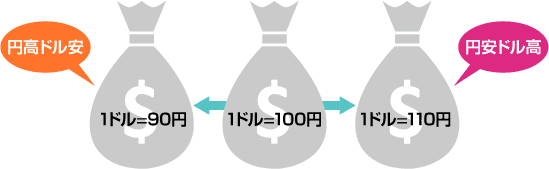
輸出企業
例)自動車を1台1万ドルでアメリカに輸出していたとします。1ドル100円のときは100万円の売り上げとなりますが、110円になると110万円の売り上げとなり、10万円増えることになります。それにより業績が良くなり、株価は上がることがあります。
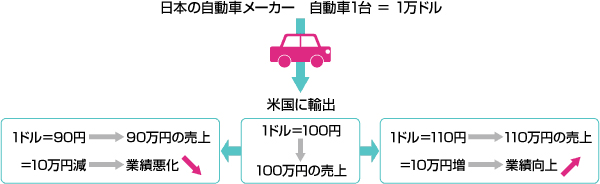
輸入企業
例)原材料を1万ドルで海外から輸入していたとします。1ドル100円のときは100万円の購入費用となりますが、90円になると90万円の購入費用となり、10万円の費用削減となります。それにより業績が良くなり、株価は上がることがあります。